太陽光発電(+蓄電池)全般
太陽光発電を企業が導入するメリットとデメリットを解説!
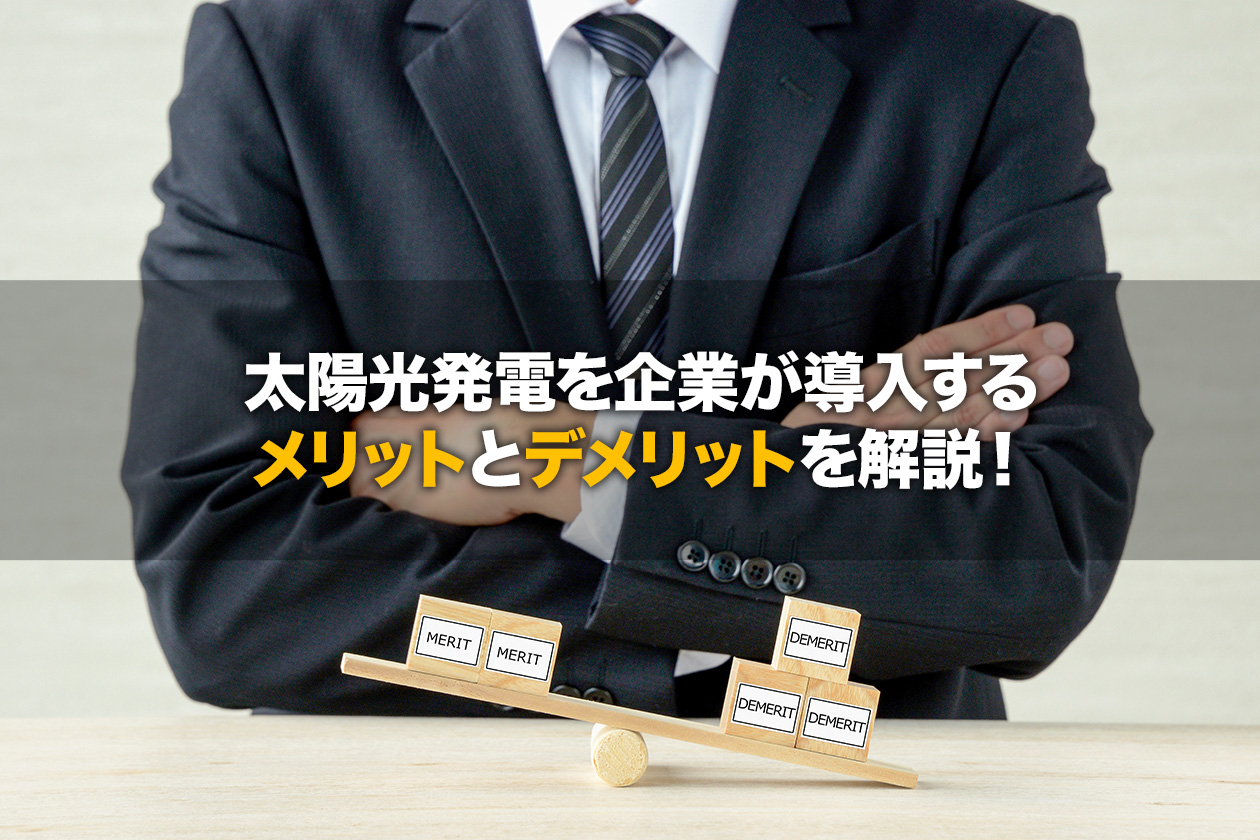
近年、SDGsやESG経営への関心の高まりから、再生エネルギーの調達手段として太陽光発電への注目が高まっていす。太陽光発電を企業が導入するメリットはどのようなものがあるでしょう。この記事では企業が太陽光発電を導入するメリットやデメリット、実際に太陽光発電を導入する方法について説明します。
太陽光発電とは?
太陽光発電とは太陽の光エネルギーを、電力に変換できる仕組みのことです。発電時に、石油・石炭などの化石燃料を使用せず、温室効果ガスの排出量が少ないため、再生可能エネルギーとして注目されています。再生可能エネルギーの導入数は年々増加しており、再エネの電源構成比は環境省によると2011年度の10.4%から2022年度の21.7%に拡大しております。
太陽電池(ソーラーパネル)で太陽光を受けて、直流の電気を生成し、パワーコンディショナーで交流の電力に変換して、家庭や事業所で使用します。産業用太陽光発電、産業用太陽光発電といった区別がされることがありますが、これは出力が10kw未満の太陽光発電を住宅用太陽光発電、10kw以上の施設を産業用太陽光発電と呼んでいます。
企業が太陽光発電を導入するメリット
企業が太陽光発電を導入するメリットについて順番に説明していきます。
環境保全につながる
太陽光発電は電力発電時に二酸化炭素を排出しないので、地球温暖化防止につながります。地球温暖化防止はSDGsの目標としても定められており、貢献することで企業イメージの向上も期待できます。また、イメージの向上というだけでなく、ESG投資家の投資による資金獲得チャンスにもつながります。ESGとは環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の3つの頭文字を取ったもので、企業が短期的な利益だけでなく長期的に持続可能な成長をしていくために必要な一つの指標です。
ESG投資家は環境問題や社会問題に配慮し、健全な企業統治が行われているかという軸も考慮して、会社に投資を行います。このように企業の環境保護活動は企業の社会的責任を果たすというだけでなく、イメージの向上や資金調達のチャンスが増えるという明確なメリットも存在します。
電気代を節約できる
太陽光発電の導入は電気代の節約になります。太陽光発電で発電した電気は、自社で消費することが可能です。近年、コロナ禍やウクライナ情勢から電気代はますます高騰を続けています。電気代が高くなっている今、太陽光発電を導入することは特に節約メリットが高くなります。電気代が一番高い時間帯に太陽光発電で発電した電気を充てることで最大電力需要を下げ、基本料金を抑えるピークカットを行うことで、電気代を大きくカットすることができます。
BCP対策になる
太陽光発電で発電した電力は蓄電池を使って蓄え非常時の電源とすることで、BCP対策になります。BCP対策とは企業が自然災害や感染症、サイバー攻撃などが発生してもなるべく迅速に通常業務に復帰するための対策のことです。太陽光発電は昼間に発電し、夜に蓄電池を使って蓄えておくことで数日間電力を供給することも可能です。
太陽光発電と蓄電池が自社にあれば災害時でも、サーバーや通信機器などを完全停止させずに継続して使用することが可能です。電力が完全停止せず外部との通信が可能な状況を維持することで、社員安全を守り、取引先やサプライチェーンの会社からも災害時に止まらない会社として評価されます。
売電収入を得ることができる
太陽光発電施設で発電した電力は、売電することで収入を得ることも可能です。特に国が一定期間の間、固定価格で買い取ってくれるFIT制度を利用すれば、使用価格よりも高い値段で売電することが可能です。余剰売電制度を利用すれば、自家消費しきれなかった分の電力も売電することで、無駄なく経済的なメリットを得ることができます。ただし、余剰売電制度は50kw未満の小規模な産業用太陽光と10kw未満の住宅用太陽光発電が対象となっております。
太陽光発電を導入するデメリット
企業が太陽光発電を導入する場合のデメリットについて説明します。
初期費用がかかる
太陽光発電を自社で導入するには、太陽光パネルやパワコンなどの設備購入費や設置工事費など決して安くはない初期費用が掛かります。経済産業省の出している「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」によると1KWあたり25.5万円となります。産業用太陽光発電の出力を30kwとすると、450万円が太陽光発電の設置に必要な初期費用となります。ただし、太陽光発電を自社で導入する際は補助金が利用できる場合があります。補助金を利用してなるべくコストを落として太陽光発電を導入しましょう。
定期的なメンテナンスが必要
太陽光発電を導入した後は定期的なメンテナンスが義務付けられています。業者を雇った定期的なメンテナンスの頻度4年に1回以上と定められており、パネルに汚れがないか目視で記入するなど日常的な点検は週に数回程度実行することが推奨されます。太陽光発電は配線の劣化やパワコンの動作異常などが重大な事故につながる可能性もあるため、定期的なメンテナンスが重要になります。
設置面積を取る
太陽光パネルを自社で導入する場合、設置面積を確保する必要があります。作業スペース等も含めた太陽光発電の1KWあたりの必要面積は、パネルの大きさによっても変わってきますが、10~15㎡と言われています。産業用の太陽光発電の出力を30kwと仮定すると必要なスペースは300㎡~450㎡となり、これはスーパーマーケットぐらいの広さとなります。近年は、オフサイトPPAやバーチャルPPAのように会社の敷地内に設置面積がない場合でも太陽光発電を導入できる方法も存在します。
太陽光発電の導入を特におすすめする業種
輸送業
物流倉庫や橋王センターは屋根の面積が膨大なため、太陽光発電の設置場所として最適です。また物流倉庫や配送センターは、照明や空調を広大な空間に効かせる必要があるため常に電力を多く消費します。よって、物流倉庫の消費電力を賄うことにより、売電をしなくても太陽光発電の導入による経済的なメリットが大きいため、輸送業は太陽光発電の導入をおすすめできる業種といえます。
製造業
製造業も電力コスト削減の観点から、太陽光発電の導入が特におすすめです。工場では多くの機器が稼働し続けているため、特に電力消費が多く高圧や特高の受電が多いです。そのため、太陽光発電による電力削減メリットが大きいです。特に、平日の昼間の電力需要が高く、太陽光発電で発電する時間と電力を消費する時間帯がかみ合っており、自家消費の効率が非常にいいです。また、工場の屋根のスペースは広大なので、太陽光パネルの設置にも適しています。
小売りサービス業
小売りサービス業、特にショッピングモールなどの大型の商業施設を持つ事業者は太陽光発電の導入を特におすすめします。商業施設の屋根は太陽光発電を設置できる広いスペースがあります。また、大型の商業施設は施設内の照明や空調によって多くの電力を消費するので、太陽光発電による電力削減メリットが大きいです。
また、太陽光発電を導入することで、「脱炭素店舗」や「再エネ利用店舗」として消費者にブランドアピールできます。商業施設に太陽光発電を設置する場合屋根だけでなく駐車場(ソーラーカーポート)に設置する方法もあります。
太陽光発電を導入する方法
太陽光発電を導入するには、自社で所有する方法かPPAで導入するかの大きく2つ方法があります。それぞれ説明していきます。
自社で購入する
太陽光発電を自社で導入する場合はEPC事業者を使いましょう。EPC事業者とは、Engineering(設計)、Procurement(調達)、Construction(建設)の3つの工程を一貫して引き受ける事業者のことです。太陽光発電の導入過程において、施設の企画から、導入、工事、メンテナンスまで一貫して請け負ってくれるので、複数の業者とのやり取りが発生せず手軽で、問題が起きオタ場合の責任の所在も明確です。
自社で購入する場合とPPAを利用する場合の大きな違いは売電が可能かどうかです。自社で所有する太陽光発電は、売電が可能で毎月無料で発電所で発電した電気を自家消費できるので、長期的に見た場合の経済的メリットが大きいです。
PPAモデルで導入する
PPAモデルとは、第三者所有モデルともいわれる、電力需要家が発電所を直接保有せずに、一定の契約期間の間、事業者が設置した太陽光発電から電力を購入するという方法のことです。自社所有との大きな違いは、初期費用が0円であるという点です。PPAモデルでは、自社で所有しないため、売電はできませんが、初期費用が掛からず、メンテナンスの必要ありません。ただし、発電所で発電した電力は毎月、PPA事業者から購入する必要があります。
自社所有とPPAどちらがいいか
太陽光発電を自社に導入する場合は、導入する目的を整理しPPAか自社所有のどちらがいいか決めましょう。自社所有の利点は長期的に見た場合の経済的メリットが高いことです。一方で、PPAのメリットは初期費用の掛からない手軽さです。
また、PPAには会社の敷地内に太陽光発電を設置するスペースがない場合でも、敷地外の場所に発電所を設置し電力を供給するオフサイトPPAや電力を直接供給せず、再生可能エネルギーの持つ環境価値だけを供給してもらうバーチャルPPAが存在します。太陽光発電を設置し、再生可能エネルギーを取り入れる際は目的に合った方法を選択しましょう。
まとめ
このように太陽光発電を導入することは企業のブランドイメージの向上、電気代の節約、BCP対策といった点で大きなメリットが存在します。一方で、高い初期費用がかかり、定期的なメンテナンスが必要といった課題もあります。ただし、PPAモデルを利用すれば初期費用0円、メンテナンス不要で手軽に太陽光発電の導入が可能になります。太陽光発電を導入する際は、目的をしっかりと整理してどのような方法で導入するか検討を尽くした上で設置しましょう。
更新日:2026年02月02日

「FIT制度」と「FIP制度」の違いをご存じでしょうか?両制度はともに日本の再生可能エネルギーの買取価格に関する制度です。では、その違いは何でしょうか?またどちらの制度が法人にとってお得でしょうか?解説していきます。
FIT制度とは?
FIT制度とは「Feed-in Tariff」の頭文字を取った略称で、国が一定期間固定の価格で、再生可能エネルギー由来の電力を買い取ってくれる制度のことです。
FIT制度導入の背景
FIT制度導入の背景には日本のエネルギー自給率の低さがありました。日本のエネルギー自給率は他の先進諸国と比べても低く、主なエネルギー源である石油・石炭・天然ガスエネルギーのほとんどを輸入に依存していました。そこで、自給率を上げるために、再生可能エネルギーの普及を狙って創設された制度がFIT制度でした。
FIT制度の成果
FIT制度は国が高い固定買取価格を保証することで投資リスクを減らし、法人や個人の発電事業者の再生エネルギー参入への障壁を下げることで、再エネの普及に貢献してきました。住宅用太陽光発電で2009年、産業用で2012年から固定価格での買取が始まってから3年間で、再生エネルギーの導入量が倍増しました。
FIT買取期間
国が固定価格で買い取ってくれる、買取期間は産業用太陽光発電が20年間、住宅用太陽光発電が10年間となっています。買取期間終了後も、電力会社と直接契約して売電を続けることは可能です。ただし、売電単価は落ちる可能性が高いです。
FIT売電単価
FITの固定価格は太陽光発電設備の発電出力によって価格は変わり、2025年上半期だと設備の出力が50kw未満の屋根設置型産業用太陽光発電の場合、FIT価格は11.5円となります。
ただし、2025年度下半期から適用される新制度「初期投資支援スキーム」によって屋根設置型の太陽光発電に対して、初めの4~5年間は買取価格が高く設定されます。250kw未満の産業用太陽光発電であれば、はじめの5年間は19円/kwh で買い取ってもらえるので、上半期と比べると2倍近く買取価格が高くなります。
FIT価格の下落
FIT制度の買取価格は太陽光発電の導入コストなどをもとに算出し、経済産業大臣が最終的に価格を決定します。近年は太陽光発電導入コストの低下とともに、売電単価も年々下落しています。現在は11.5円の産業用太陽光発電の売電単価も、導入当初の同規模設備の買取価格は40円/kwhでした。
FIP制度とは?
FIP制度とは、買取期間の間、固定される「基準価格」に毎月市場によって変動する「プレミアム」を加えた額で再生エネルギー電力を売電できる制度のことです。
FIP制度導入の背景
日本政府は2050年までに、温室効果ガスの排出量と削減量を差し引きでゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指しています。そのためのステップとして、2030年までに温室効果ガスを46%削減することを目標として掲げており、さらなる再生エネルギーの普及のためFIP制度は導入されました。
FIP制度にはプレミアの付与によって事業者の投資意欲を促進し、FIT制度で普及した太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを、事業者が電力市場の市場原理に基づいて取引できるよう促すことで、再び電力市場へ統合するという目的があります。
また、FIP制度には再エネ賦課金の負担を下げる役割も期待されています。 FIT制度では市場よりも高い固定価格で取引するために、再エネ賦課金が電気代に上乗せされることで国民の負担になっていました。このような負担を軽減するためにもFIPによる市場価格での取引への移行が急がれます。
FIP認定を受けることができる発電施設
現在FIP制度の認定を受けることができる太陽光発電設備は出力が50kw以上の産業用太陽光発電となっております。出力が50kw未満の産業用太陽光発電や住宅用太陽光発電はFIP制度の認定を受けることができません。
また、出力が250kw以上の太陽光発電設備は自動的にFIP制度が適用されます。このように、今はまだ適用範囲が限定的なFIP制度ですが、今後は適用範囲を徐々に広げていくと考えられております。
また、すでにFIT制度を適用している太陽光発電設備でも、申請すればFIP制度に移行することが可能です。
FIPの売電価格
FITの売電価格は、買取期間の間固定される基準価格に市場の状況によって変化するプレミアを足した額となります。基準価格はFITの買取価格と同じように導入コストなどから決定され、申請年度から20年間固定されます。FIP制度におけるプレアムは、基準価格から参照価格を引いた差額になります。
参照価格の内訳は、卸電力市場の価格に連動して算定される金額と非化石価値取引市場の価格に連動して算定される金額からバランシングコストを引いたものになっています。
参照価格の具体的な計算式は以下の通りです。
参照価格 = 前年度年間平均市場価格 + (当年度月間平均市場価格 – 前年度月間平均市場価格) + 非化石価値市場収入 – バランシングコスト
売電単価は毎月変動しますが、電力市場の状況によってはFIT価格よりも高い値段で売電できる可能性も存在します
バランシングコスト
バランシングコストとは電力事業者が事前に提出する需要量の予想と実際に消費した供給量の差を埋めるために事業者が支払う料金のことです。FIP制度では、発電事業者は事前に発電計画を立て、見込まれる需要量と実績値と一致させる「バランシング」が義務として求められます。
FIT制度とFIP制度の違い
FIT制度とFIP制度にはいくつか違いが存在します。
1つ目が、再エネ電力の買取価格です。FIT制度では産業用では20年間、住宅用では10年間の間固定価格で太陽光をはじめとする再エネ電力を買い取ってもらえます。一方で、FIP制度の場合は基準価格は20年間固定されますが、プレミアが毎月の電力や非化石市場の状況によって変動します。
2つ目が、制度の適用範囲です。 FIT制度は出力が250kw未満の太陽光発電施設に適用することが可能です。一方で、FIP制度は出力が50kw以上の太陽光発電施設から適用を選択できます。 また、出力が250kw以上の太陽光発電施設は自動的にFIPが適用されます。
FIT制度メリット
FIT制度のメリットは大きく2つあります
・ 収入の見通しが立つ
・ インバランス料金を負担しなくていい
詳しく見ていきましょう
収入の見通しが立つ
FIT制度は決まった買取期間、固定価格で再エネ電力を買い取ってくれます。出力が10kw以上の産業用太陽光発電であれば、買取期間は20年間です。20年間FIT申請が認定された年度の買取価格で電力を売ることができます。よって、どれだけの収益を太陽光発電によって得ることができるか計算が容易で収益の見通しが立ちます。
インバランス料金を負担しなくていい
FIT制度では見込まれる電力の需要量と実際の電力の消費量の差を清算するためのコストであるインバランス料金を支払う必要がありません。FIP制度では事前に需要量を予測し、実測値と一致させるバランシングをする必要がありますが、FIT制度が適用されている場合は、インバランス特例で免責となります。
FIT制度デメリット
一方で、FIT制度のデメリットは大きく2点あります。
・収入が上振れることはない
・非化石価値取引市場で取引できない
それぞれ見ていきましょう
収入が上振れることはない
前述したようにFITによる固定価格買い取り期間の間は、売電単価が固定されます。 そのため、長期間安定した収入を稼げる一方、売電収入が高くなるということもありません。
再エネ賦課金が軽減できない
FITによる固定買取価格が市場価格より高めな理由として、再エネ賦課金を国民の電気代から負担していることが挙げられます。ただし、これは国民全体に負担をかけている状態なのであまり好ましいとは言えません。
また、近年ウクライナ情勢によるエネルギー不足から電気代が高くなっていることもあって、いくらFIT制度を使って高い価格で売電できても、その分電気代が高くなているのでは元を取れているとは言いづらいです。
FIP制度メリット
FIP制度のメリットは主に以下の2つ存在します。
・収益の最大化を目指すことができる
・間接的に再エネ賦課金の軽減に貢献できる
詳しく見ていきましょう。
収益の最大化を目指すことができる
FIP制度は買取期間に固定される基準価格に加えて、市場によって変動するプレミアを加えて電力を売ることができます。 そのため、市場で電力の価格が高い時期により多くの電力を売電すれば、より多くの売電収入を得ることができ収益の最大化を目指すことができます。
間接的に再エネ賦課金の軽減に貢献できる
FIP制度も、プレミアムが加算される優遇制度であるので直接再エネ賦課金の軽減には貢献しませんが、FIPの普及により再生可能エネルギーの電力市場での取引がより一般的になり、電力市場全体のシステムが効率化しコストが削減できれば、再エネ賦課金の軽減につながります。
FIP制度デメリット
FIP制度のデメリットとしては大きく以下の2つが考えられます。
・収入の見通しがたたない
・インバランス料金を負担する必要がある
それぞれ見ていきましょう
収入の見通しがたたない
FIP制度の売電価格は市場の状況によっては、上がるだけでなく当然下がることもあります。よって、固定された金額で長期間売電できるFIT制度と比べて、安定した収入の見通しを立てることは難しいでしょう。
インバランス料金を負担する必要がある
インバランス料金とは需要予測と実際の使用量にずれが生じた場合に、そのずれに対して電力事業者が一般送配電事業者に対して支払う料金のことです。 FIT制度では免責になっていたインバランス料金をFIP制度だと支払う必要があります。
法人にとってどちらがお得?
どちらがお得であるか、発電施設や電力市場の状況にもよりますので一概には言えません。あえて結論を出すならば、安定した収入を取るならFIT制度、収益の最大化を目指すならFIP制度ががおすすめです。理由はこれまで述べてきたように、FITであれば固定価格で売電でき、FIP制度ならばプレミアによって収入の上振れを期待できるからです。
ただし、どちらの制度を適用にするにしても現在(2025年8月)であれば初期投資支援スキームを利用することがおすすめです
2025年下半期から導入された「初期投資支援スキーム」は、FIT/FIP初期の売電価格を上げ、初期投資を手早く回収させることが狙いで設立されたスキームです。初期投資支援スキームにより、2025年下半期の屋根設置型太陽光発電システムの売電価格は上半期と比べて、11.5➡19円と2倍近くも上昇しております。
初期投資支援スキームは発電事業者に太陽光発電の初期費用を手早く回収してもらうために設立されたスキームなので、上記の売電価格は5年目までで6年目以降は下がってしまいます。しかし、初期投資を早く回収できるというだけでも大きなメリットと言えるのではないでしょうか?
また、補足にはなりますがFIT/FIPのどちらかを選ぶ場合、長期的に見ればFIP制度がおすすめです。理由としては、再エネ賦課金の間接的な軽減効果が期待できるからです。前述したようにFIPの普及により再エネ電力の電力市場での取引が一般化し、電力市場全体のコストダウンによる効率化が起きれば、長期的にではありますが再エネ賦課金の軽減に貢献し、電気代の削減にもつながる可能性があります。
また、現在FIP制度は50kw以上の太陽光発電にのみ適用可能ですが、今後その範囲は広がっていき、徐々にFIT制度からFIP制度への移行が進むと考えられています。
長くなったのでまとめます。
安定した収入を取るならFIT制度が、収入の上振れや長期的な観点で見るとFIP制度がおすすめです。ただし、どちらの制度を適用するにしても2025年8月現在では,初期投資支援スキームを利用することがおすすめです。
更新日:2025年11月26日

よく「太陽光発電が売電できなくなる」「FIT制度は終了する」といった噂を聞くことがありますが、実際のところどうなのでしょうか?本記事では、なぜ「太陽光発電は売電できなくなる?」といった噂が広まったのか原因を考察し、FIT卒業後の効果的な太陽光発電設備の活用方法を紹介します。
太陽光発電は売電できなくなるのか?
結論から言うと太陽光発電は売電できなくなるわけではありません。
また、FIT制度も終了しません。
このような噂が広がった原因としてFIT制度の買取期間が終了することを、太陽光発電で売電できなくなることやFITの制度自体が終了することと勘違いした可能性があります。
また、今ではあまり聞かなくなりましたが、「2019年問題」というワードが話題になった時期がありました。この「2019年問題」というワードが話題になったことで、「太陽光発電は売電できなくなる?」といった噂が広まった可能性もあります。
2019年問題とは
2019年問題とはFIT制度が、住宅用太陽光発電に向けて開始された2009年に売電を開始した発電事業者が、買取期間終了後の2019年度に、買取価格が大幅に下がった余剰電力をどう売電するかという問題です。
2025年現在では1kwhあたり15円(住宅用)の売電単価も、FIT制度導入当時は48円/kWhと非常に高額でした。そのため、2009年度に太陽光発電を導入した世帯は多く、影響を受ける世帯は50万世帯以上にのぼります。
影響を受ける事業者は主に10kw以下の住宅用太陽光発電を設置していた事業者で、産業用太陽光発電を設置した事業者は買取期間終了が2012年から20年後の2032年とまだ先なので、しばらくは影響を受けないでしょう。
2019年問題が大きく話題になった要因としてFIT卒業後の売電価格の想定が大幅に下がったことが考えられます。当初の想定では、24円/kwhだった売電価格は、11円/kwhになると2016年に経産省から発表されました。
そのため、2009年ごろに太陽光発電を導入した事業者たちの卒FIT後の収支シミュレーションが大きく崩れることになりました。なお、現在2025年の売電単価はさらに下がり、約8.0円/kwhほどです
この2019年問題によって発生した混乱を、まだ太陽光発電を導入しようか検討している段階の発電事業者が目にして、「太陽光発電は売電できなくなる?」「FIT制度が終了する?」といった誤解を生んだのではないかと考えられます。
2025年現在もFIT制度は継続し売電も可能ですが、今後はどうなるでしょうか?
FIT制度は今後どうなる?
FIT制度とは?
FIT制度とはFeed-in Tariffの頭文字を取った略称で、決められた期間の間、国に固定の価格で太陽光発電設備で発電した電力などの再生可能エネルギーを買い取ってもらうことができる制度のことです。
買取期間は産業用(10kw以上)太陽光発電で20年間、住宅用で10年間となっています。決められた買取期間の間、通常よりも高く再エネで発電した電力を買い取ってもらうことができます。
買取期間終了後も太陽光発電で発電した電力を売電することは可能です。 また、FIT制度自体も2025年現在終了しておらず今から太陽光発電を導入する事業者でも制度の適用は可能です。ただし、買取期間終了後は買取価格が大幅に下がってしまいます。
FIT制度は産業用で2012年から、住宅用で2009年から制度の運用が開始しております。
FIT制度価格推移
FIT制度の売電単価は年々下がっております。
| 産業用太陽光発電(50kw未満) | 売電単価 |
|---|---|
| 2012年度 | 40円 |
| 2013年度 | 36円 |
| 2014年度 | 32円 |
| 2015年度 | 29円/kWh(4/1~6/30)、27円/kWh(7/1~) |
| 2023年度 | 10円(4-9月) 12円(10-3月) |
| 2024年度 | 12円 |
| 2025年度 | 11.5円 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円 |
新電力ネット
https://pps-net.org/fit_kakaku上の表は屋根設置型の産業用太陽光発電(50kw未満)の売電単価の推移をまとめたものです。導入当初2012年度の売電単価は40円/kwhであるのに対して、2025年度の売電単価は11.5円/kwhとなっており大幅に下落していることがわかります。FIT制度による売電価格の下落は今後も続くと予想されます。
なぜなら、FIT制度の固定価格は太陽光発電設置にかかるコストを基準に、決定する仕組みになっており、導入コストは今後も低下傾向にあるからです。
また、FIT制度はFIP制度に徐々に移行すると考えられております。
FIP制度への移行
FIP制度とは、FIT制度で普及した太陽光をはじめとする再エネ電力を、電力市場に統合することを目指して設立された制度です。
FIT制度と同じように、発電施設導入に必要な費用をもとに策定された「基準価格」に、毎月市場によって変動する「プレミアム」を加えた額で、再エネ電力を売電できる仕組みになっており、そのため売電価格は毎月変動します。
現在では、50kw以上の発電出力を持つ太陽光発電はFIP制度がFIT制度を適用するか選択が可能で、250kw以上の出力を持つ太陽光発電はFIP制度が適用されます。
FIP制度が適用される範囲は今後拡大していくと考えられています。
このようにFITの売電単価が低下し、FIPへの移行が徐々に始まっておりますが、太陽光発電の売電自体は今後も可能であると思われます。
一方で、売電自体は可能でもFIT卒業後に大幅に売電単価が下がってしまうこともまた事実です。
では、FITの買取期間満了後にはどのようにして、太陽光発電を有効活用できるでしょうか?FIT卒業後に取れる選択を5つほど紹介します。
卒FIT後に産業用太陽光を活用する5つの選択肢
FITの買取期間を終了することを、一般的に卒FITと言います。
卒FIT後に産業用太陽光発電を活用する方法を5つほど紹介します。
そのまま売電契約を継続する
1つ目は、契約する電力が会社を変えず、そのまま売電を続ける方法です。
FITの固定買取期間終了の3~4か月前に、契約している電力会社から買取期間終了の通知がきますが、 基本的に再契約や更新の手続きをせず、買取契約が自動更新される電力会社がほとんどです。
ただし、FIT期間と比べるとどうしても売電単価が下がってしまいます。
以下に、地域の大手電力会社の電力買取単価をまとめてみました!
| 地域電力 | 売電単価 |
|---|---|
| 北海道電力 | 8.0円 |
| 東北電力 | 9.0円 |
| 東京電力 | 8.5円 |
| 中部電力 | 8.0円(プレミアムプラン) |
| 北陸電力 | 8.0円(簡単固定プラン) |
| 関西電力 | 8.0円 |
| 中国電力 | 7.15円 |
| 四国電力 | 7.0円 |
| 九州電力 | 7.0円 |
| 沖縄電力 | 7.7円/kWh(税込、消費税率10%):10kW未満 8.2円/kWh(税込、消費税率10%):10kW以上(本島) |
このように、現在の大手電力が視野の電力買取プランでは、1kwh当たり8円程度が相場</span>と言えます。
FIT期間と比べると売電単価は落ちますが、収入を得ること自体は可能なうえ、面倒な手続きや再契約は一切必要ありません。
こちらの方法はFIT終了後も手軽に稼ぎたい人におすすめです。
売電単価が高い電力会社と再契約する
2つ目は、より買取価格が高い電力会社と契約しなおすことです。
FIT期間終了後、現在契約している電力会社で充分な売電収入が期待できない場合は、契約を取り消して別の電力会社に余剰電力を売電するということも可能です。
電力会社によっては卒FIT後も高価買取可能なプランが存在します。
| 東京ガス | 太陽光買取プラン 10.5円/kwh 蓄電池購入サポートプラン 23円(半年間だけ) |
|---|---|
| ENEOS | 東京エリア 11円/kwh 関西エリア 10円/kwh |
東京ガス
https://home.tokyo-gas.co.jp/housing/eco_equipment/solar_battery/fit_purchase/index.htmlENEOS
https://www.eneos-power.co.jp/solar-kaitori/?ag_code1=9503&ag_code2=0001例えば、東京ガスの太陽光買取プランであれば、FIT終了後も1kwh当たり10.5円で電力を買い取ってくれます。卒FIT後の売電単価の相場は1kwh当たり約8円ほどなので、かなりお得といえます。また、プランの適用期間も特に定まっておらず、ずっと高い値段で売電することが可能です。
また、同じく東京ガスの蓄電池購入サポートプランでは、東京ガス指定の販売店で対象の蓄電池を購入した方限定で、1kwhあたり23円で売電することが可能です。
ただし、こちらの期限は半年となります。
東京ガスの他にENEOSも高額買取プランを実施しています。
買取単価はエリアによって変わりますが、東京エリアで11円、関西エリア10円となっています。
買取単価適用の条件は特になく、FIT期間終了後に手続きをすれば簡単に契約可能です。
自家消費量を増やす
3つ目は、余剰電力を売電せずに自家消費量を増やすという方法です。
昨今電気代が高騰していることもあって、この方法が特におすすめです。
近年、コロナの流行やウクライナ情勢によるエネルギー需要の上昇から、電気代が高騰し続けているため、自家消費でより多くの電気代を削減することができるようになっています。
電気代の1kwh当たりの単価は電力会社によっても変わってきますが、一つの基準として全国家庭電気製品公正取引協議会の出している、新電力料金目安単価を参照すると31円が目安の電気代単価<として定められております。
この価格は、2025年度の住宅用太陽光発電のFIT価格15円と比較しても倍以上の差があります。つまり、自家消費量を増やせばその分だけ電気代を削減できるということです。
また、初期費用は掛かってしまいますが、自家消費量を上げるためには蓄電池の導入もおすすめです。
蓄電池を導入すれば、昼間の間に自家消費できなかった分の電力を貯蓄し夜に使用することで自家消費率を上げることができます。災害時に電力を供給することも可能で企業にとってBCP対策になります。
自家消費額の試算
自家消費によって節約した電気代を計算してみましょう。
太陽光発電協会によると、1kwの出力の太陽光発電が年間に発電する発電量は1000kwh よって、 30kwの産業用太陽光発電の年間発電量は30000kwh。
また、屋根設置型の太陽光発電の年間売電自家消費率は、 経済産業省の資料によると(https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/100_01_00.pdf)平均して約46%と言われております。つまり、1年間で自家消費した電力量は、30000×0.46=13800kwhとなります。
新電力料金目安単価を参照して1kwh当たりの電力単価を31円とすると、
年間に削減した電気代は、13800×31=427800円(42万7千800円)となります。
先ほど試算した、年間の売電収益と合わせると、おおよその数値にはなりますが年間約60万円程度の費用を回収できていることがわかります。
発電所の売却
4つ目はFIT期間を終えた発電所を売却する方法です。太陽光発電にはセカンダリー市場と呼ばれる、すでに稼働している中古の発電所を売買する市場が存在します。
FIT期間の終了により十分な収益を見込めないと感じたならば、中古市場へ売り出してみるのも選択肢としてはありです。売却する設備の売電実績や状況によっては、高い売却益を期待できます。
また、売却益の他にも維持コストの削減や余った土地の有効活用ができるといったメリットが存在します。売却益や浮いた維持費、空いた土地でで新たな事業投資を開始することも可能です。
ただし、売却益には税金がかかるることに注意が必要です。売却益-(購入金額-減価償却費)がプラスになり、利益が発生した場合はその利益に対して税金がかかります。
更新日:2025年11月26日

住宅用太陽光発電と産業用太陽光発電の違いとは何でしょうか?
上記の言葉は太陽光発電について調べる際にしばしば見かける言葉だと思います。
では、具体的にどう違うのでしょうか?
本記事では住宅用太陽光発電と産業用太陽光発電の違いを徹底的に解説し、産業用太陽光発電の設置費用やなるべく安く導入する方法をシミュレーションしております。
一括お見積もりサービスはこちら!
ソーラーマッチ(仮)
産業用太陽光/住宅用太陽光発電の違い
産業用太陽光発電とは10kw以上の出力を持つ、主に工場、倉庫、遊休地で使われる太陽光発電設備のことを指します。一方で、出力が10kw未満で主に住宅で使用される太陽光発電設備を住宅用太陽光発電と呼びます。
住宅用/産業用という名称ですが出力差による区分なので、個人所有の太陽光発電でも出力が10kwを超えれば産業用太陽光発電と呼称されます。同様に法人所有の設備でもっ出力が10kw未満ならば産業用太陽光発電と呼称します。
出力とは
太陽光発電の出力(kw)とは、瞬間的に最大で何KWの電力を発電できるかを示した数値です。例えば、出力400kwのパネルを12枚設置したとすると、0.4×12=4.8kwが設置した太陽光発電施設の瞬間最大発電能力となります。
太陽光パネルとパワーコンディショナーそれぞれに発電出力が存在しますが、出力量の合計が低い方に合わせます。パワーコンディショナーとは太陽光発電設備が発電した「直流」の電力を、電力会社から送られてくる電力と同じ「交流」に変換する装置です。
私たちが普段コンセントを通して使用する電力は【交流」の電力で、「直流」の電力のままでは使用できません。つまり、パワーコンディショナーの出力を超える出力の太陽光パネルを設置しても、超えた分の電力は使用できないということになります。
一般的な産業用/住宅用太陽光発電の出力
住宅用太陽光発電設備の平均出力は4~5kwと言われております。
他方、産業用太陽光発電では導入する施設の設置可能面積により様々で、小規模な工場や倉庫の屋上に設置するような数十kwの設備もあれば、広大な空きスペースを利用した1mw(1000kw)を超える出力を持つ太陽光発電も存在します。この1MW超える超大規模な太陽光発電施設のことをメガソーラーと呼びます。
住宅用/産業用太陽光発電の買取制度の違い
| 産業用太陽光発電 (50kw以上/地上) |
産業用太陽光発電 (10kw以上/屋根) |
住宅用太陽光発電 | |
|---|---|---|---|
| 買取期間 | 20年間 | 20年間 | 10年間 |
| 売電単価 | 8.9円 | 11.5円 | 15円 |
出典:資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html住宅用太陽光発電と産業用太陽光発電の大きな違いとして、売電開始後に適用可能な買取制度の違いが存在します。
余剰買取制度と全量買取制度
余剰買取制度とは自家消費後に余った電力を電力会社に売電する制度のことです。一方で、全量買取制度は発電した電力のすべてを売電する制度のことです。
出力が50kw以上の産業用太陽光発電設備の場合、全量買取か余剰買取を選択することができます。
一方で、出力が10kw未満の住宅用太陽光発電や産業用太陽光発電でも50kw超えない施設は余剰買取制度しか利用することができません。つまり、50kwを超えない施設の場合、主な使用目的は自家消費となり、余った分のみを売電できます。
FIT期間の違い
FIT制度とは決められた期間の間、国が太陽光などの再生可能エネルギーなどで発電された電力を、固定金額で買い取る制度のことです。産業用太陽光発電と住宅用太陽光発電ではこの買取期間が変わってきます。
出力が10kw以上の産業用太陽光発電の買取期間は20年間で、 10kw未満の住宅用太陽光発電は10年間となっています。
住宅用太陽光発電は産業用太陽光発電と比べてFIT期間が短いですが、そのかわり1kwh当たりの売電単価が高く設定されております。
売電単価の違い
産業用と住宅用の太陽光発電では1kwhあたりの売電単価も変わってきます。1kwhという単位は、電力の単位KWに時間をかけた、発電量の単位です。1kwの出力で1時間発電した際の電力量が1kwhです。
2025年度の産業用太陽光発電の1kwh当たりの売電単価は、10kW以上250kw未満の屋根設置型太陽光発電で11.5円、50kw以上250kw未満のの地上設置型施設で8.9円となっております。一方で、出力が10kw未満の住宅用太陽光発電は15円となっております。
FIT制度による売電単価は年度によって変わりますが、定められた買取期間であれば認定された年度の単価で電力を売ることができます。
売電収入シミュレーション
では、太陽光発電を導入しFIT制度を使って売電する場合、いくらぐらい稼げるのでしょうか?住宅用/産業用(10kw以上/屋根)/産業用(50kw以上/地上)の3つの場合に分けてシミュレーションしてみました!
住宅用太陽光発電の年間売電収入
太陽光発電協会によると、出力が1kwの太陽光発電の年間発電量は約1000kwhだそうです。
住宅用太陽光発電の発電出力を平均的な5kwと仮定すると、5kwの住宅用太陽光発電の年間発電量は5000kwhになります。
5kwの住宅用太陽光発電の場合、余剰売電制度が適用されるので自家消費した分は売電できません。
太陽光発電協会によると(出展を記載)住宅用太陽光発電の自家消費率はおおよそ3割と言われています。
この値をもとに売電した電力の量を計算すると、5000×0.7=3500kwhとなります。
5kwの太陽光発電の売電単価は1kwhあたり15円なので、年間5万2500円の売電収入が入る計算になります。
産業用太陽光発電(50kw未満)の年間売電収入
産業用太陽光発電(50kw未満)は設置する施設により大きく変わりますが、ひとまず中小規模の工場や飲食店の屋根へ設置する場合を想定し、30kwと仮定します。
30kwの産業用太陽光発電の年間発電量は30000kwh
経済産業省の資料によると(https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/100_01_00.pdf)、屋根設置型産業用太陽光発電の自家消費率の平均は近年だと約46%であることがわかります。
4.6割を自家消費したとすると、売電した電力は30000×0.54=16200kwh
売電単価は1kwhあたり11.5円なので、11.5×16200=186300円 年間の売電収入は、18万6千300円と想定されます。
産業用太陽光発電(50kw以上)の年間売電収入
大規模な工場や商業施設に設置する太陽光発電の規模を200kwと仮定します。200kwの太陽光発電の場合、全量売電制度が適用できるので、発電した電気の全額売電する場合を想定します。
200kwの産業用太陽光発電の年間発電量は200000kwh
売電単価は1kwhあたり8.9円なので、売電収入は200000×8.9=1780000
年間の売電収入は178万円となります。
このように大型の産業用太陽光発電は全量売電が可能なため、比較的多くの売電収入が稼げます。一方で、発電した電力を売電するのではなく、自家消費+余剰売電という選択肢もあります。実際の発電量や電力の使用量によっても変わってきますが、近年は特に自家消費がおすすめです!
自家消費をおすすめする理由
自家消費をおすすめする理由は、電気代の高騰です。
近年、コロナの流行やウクライナ情勢によるエネルギー需要の上昇から、電気代が高騰し続けています。
電気代の1kwh当たりの単価は電力会社によっても変わってきますが、一つの基準として全国家庭電気製品公正取引協議会の出している、新電力料金目安単価を参照すると31円が目安の電気代単価として定められております。
この価格は、2025年度の住宅用太陽光発電のFIT価格15円と比較しても倍以上の差があります。
つまり、自家消費したほうが2倍以上もお得ということになります。
ただし大規模な物流倉庫に設置する場合など、自社の施設でも消費しきれないような電力を発電している場合はその限りではありません。
産業用/住宅用太陽光発電の必要面積をシミュレーション
では、実際に太陽光発電を導入する場合、必要な面積はどれぐらいでしょうか?以下に簡単にシミュレーションしてみます。太陽光パネル1枚の大きさは、メーカーにもよりますが約1.7㎡ほどになります。
太陽光パネルの設置に必要な面積とはパネルの設置面積だけでなく、パネル同士の隙間やメンテナンス用の作業スペースなどが入ってきます。
作業スペース等も含めた太陽光発電の1KWあたりの必要面積は、パネルの大きさによっても変わってきますが、10~~15㎡と言われています。
平均的な住宅用太陽光発電設備の出力を5kwと仮定すると、住宅用太陽光発電の設置に必要な面積は50~75㎡と想定されます。
一般的な2階建て住宅の屋根面積が50~80㎡と言われているので、上記の試算とおおよそ一致します。
産業用太陽光の発電出力を30kwとすると、1KWの設備の設置に必要な面積が10~~15㎡なので、必要スペースは300㎡~450㎡となります。
300㎡というと大体スーパーマーケットぐらいの広さとなります。
産業用/住宅用太陽光発電の必要費用をシミュレーション
次に太陽光発電施設の設置費用をシミュレーションしてみます。
太陽光発電の設置費用とは太陽光パネルの購入費だけでなく、工事費用やパワコン費用、架台費用などを含めた費用です。
内訳として一番大きいのは、パネル>工事費>架台やパワコンなどとなります。
住宅用太陽光発電の1kwあたりの設置費用は経済産業省の出している「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」によると1KWあたり25.5万円となります。
住宅用太陽光の出力を5kwと仮定すると、127.5万円が住宅用太陽光発電の設置費用と想定されます。
他方で、産業用太陽光発電の1kwあたりの必要経費は屋根設置(10kW〜50kW):15.0万円/kWと住宅用太陽光発電と比べて安くなります。これは設置するKW数が大きくなっても工事費や人件費が、大きく変わらないためです。
産業用太陽光発電の出力を30kwとすると、450万円が必要経費となります。
実際の費用は設置する太陽光発電の規模や設置する場所、利用するパネルメーカーによっても変わってきます。 太陽光発電の導入を検討している方はぜひソーラーマッチでお見積もりを
一括お見積もりサービスはこちら!
ソーラーマッチ(仮)
なるべく安く導入する方法
このように太陽光発電を導入するとなると、住宅用にせよ産業用にせよ決して安くない金額が初期費用としてかかります。
そこで初期費用0円で手軽に太陽光発電を始める方法を紹介します
PPA
PPAモデルを使用すれば、初期費用0円で手軽に太陽光発電を始めることができるのでおすすめです。PPAモデルとはPPA事業者と電力を使用する需要家が、10年から20年間にわたる長期契約契約を結び、太陽光発電を設置してもらう契約形態のことです。
企業などの需要家は太陽光発電の購入費や設置費用の負担なく、太陽光発電で発電した電力を利用することができます。
ただし、設置した施設から供給してもらった電力は、有償で事業者から購入する必要があります。契約終了後は需要家に発電施設が譲渡されることが一般的です。
PPAにはオンサイトPPAとオフサイトPPAが存在しします。オンサイトPPAとは企業や家庭などで自社敷地内に発電施設を設置し、電力を供給してもらうPPA契約のことです。
オフサイトPPAとは企業や家庭などで自社から離れた場所にある発電施設から、 電力会社の配電網を使って割安の値段で電力を供給してもらうPPA契約のことで、オフサイトPPAを使用すれば、初期費用0円で会社内に設置スペースがない場合でも、太陽光発電を始めて電気代の削減や環境問題への貢献が可能です。
補助金
太陽光発電をなるべく安く導入するためには、補助金の利用もおすすめです。住宅用/産業用でそれぞれ設備の導入に使える補助金が出ています。| 補助金名 | 令和7年度東京ゼロエミ住宅普及促進事業 |
|---|---|
| 公募期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
| 補助率 | オール電化住宅で3.6kWまでの場合 13万円/kW オール電化住宅以外で3.6kWまでの場合 12万円/KW ほかにも補助対象あり、詳細は下記URLから |
| 事業者HP | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/tokyo_zero_emission_house/tokyo_zero_emission_house_r07_fukyu |
| 補助金名 | 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業< |
|---|---|
| 公募期間 | 一次公募期間 令和7年4月3日(木)~ 5月8日(木)正午まで 二次公募期間 令和7年6月5日(木)~ 7月3日(木)正午まで |
| 補助率 | 3分の1(上限は1億円) |
| 事業者HP | https://www.eta.or.jp/ |
補助金一覧はこちら!
ソーラーマッチ(仮)
このように補助金やPPAを利用すれば安く太陽光発電を始めることができます。太陽光発電の導入を検討している方はぜひ一度ソーラーマッチでお見積もりを
一括お見積もりサービスはこちら!
ソーラーマッチ(仮)
更新日:2025年11月26日
太陽光発電の売電価格はいくら?今後の価格推移も予測!

固定価格買取制度(FIT制度)では年度ごとに、買い取り額が変わっています。
では、2025年度現在の買取価格はいくらなのでしょうか?
産業用/住宅用も含めて現在の買取価格を紹介します。
また、年々下落傾向にあるといわれているFIT価格の推移や
なぜ下落しているのかについてもご紹介いたします。
FIT制度について
FIT制度とはFeed-in Tariff」の頭文字を取った略称で、決められた期間の間、国に固定の価格で太陽光発電設備で発電した電力などの再生可能エネルギーを買い取ってもらうことができる制度のことです。
FIT制度を適用するには太陽光発電設備を設置した後、経済産業省に申請書を提出して事業計画を認定してもらう必要があります。その後、電力会社の送配電網につなぐために、系統連系申請をすることで売電が可能になります。
調達価格(買取価格)は年度ごとに異なり、決められた買取期間の間、FIT制度の適用を開始した年度の金額で売電することが可能です。
買取期間は産業用太陽光発電で20年間、住宅用太陽光発電で10年間です。
以下に1kwh当たりの買取価格を表にまとめてみました!
| 産業用太陽光発電 (50kw以上) |
産業用太陽光発電 (50kw未満) |
住宅用太陽光発電 | |
|---|---|---|---|
| 買取期間 | 20年間 | 20年間 | 10年間 |
| 売電単価 | 8.9円 | 11.5円 | 15円 |
資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html2025年度の産業用太陽光発電の1kwh当たりの売電単価は、10kW以上50kW未満の施設で10円、50kw以上の施設で8.9円となっております。一方で、出力が10kw未満の住宅用太陽光発電は15円となっております。
2025年度下半期に価格の変動あり!
2025年度下半期から適用される新制度「初期投資支援スキーム」によって屋根設置型の太陽光発電に対して、初めの4~5年間は買取価格が高く設定されます。
| 住宅用太陽光発電(10kw未満) | はじめの4年間は24円/kwh 上半期は15円 |
|---|---|
| 産業用太陽光発電(250kw未満) | はじめの5年間は19円/kwh 上半期は11.5円 |
出典:資源エネルギー庁
https://pps-net.org/fit_kakakuこのように2倍近くも買取価格が上昇します。
初めの4~5年間が終了した後は、買取価格が低下します(住宅用/産業用ともに8.3円/kwh)が、この制度を利用すれば初期投資を素早く回収することができるでしょう。
FIT価格の推移
改めてFIT制度とは、再生エネルギーを用いた発電を普及させるという目的のために、2012年度から開始した国が再生可能エネルギー由来の電力を一定の期間固定の価格で買い取ってくれる制度のことです。
その背景には日本におけるエネルギー自給率の低さや環境問題への対策のため再エネ導入率を増やすという目的がありました。
制度の開始当初の買取価格は1kwh当たり、住宅用太陽光発電で42円/kwh、産業用太陽光発電で40円/kwhと非常に高額でした。
FIT制度は創設以来約4年間で再エネの導入量が約2.5倍になるといった大きな効果をもたらしましたが、買取価格は年々下がっていく傾向にあります。
以下の表で10kw以上50kw未満の屋根設置型産業用太陽光発電に絞って価格の推移をみていきましょう。
| 産業用太陽光発電(50kw未満) | 売電単価 |
|---|---|
| 2012年度 | 40円 |
| 2013年度 | 36円 |
| 2014年度 | 32円 |
| 2015年度 | 29円/kWh(4/1~6/30)、27円/kWh(7/1~) |
| 2016年度 | 24円/kWh |
| 2017年度 | 21円 |
| 2018年度 | 18円 |
| 2019年度 | 14円 |
| 2020年度 | 13円 |
| 2021年度 | 12円 |
| 2022年度 | 11円 |
| 2023年度 | 10円(4-9月) 12円(10-3月) |
| 2024年度 | 12円 |
| 2025年度 | 11.5円 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円 |
新電力ネット
https://pps-net.org/fit_kakakuこのように、制度の導入初期と比べてかなりの金額、買取価格が下がっていることがわかります。なぜこのように、買取価格は下落しているのでしょうか?
なぜ下落している?
理由は主に2つあると思われます。
1つ目の理由が、太陽光発電の設置費用が下がっていることです。そもそもFIT制度の売電単価は、太陽光発電設置にかかるコストを基準に調達価格等算定委員会の意見を勘案して、経済産業大臣が最終的な設定をする仕組みになっています。
そのため、太陽光発電の導入コストが下がると、売電単価も下がります。
経済産業省の「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」によると、近年、太陽光導入にかかるシステム費用は低下傾向にあります。
つまり、太陽光発電の普及により導入コストが下がったため、売電単価も下がったといえるでしょう。
2つ目の理由が、再エネ賦課金が上がっていることにあります。
再エネ賦課金とは再生可能エネルギー買取のために、電力会社が費やした費用を国が補填するためのもので、電気代の一部として利用者から徴収されます。
近年、太陽光発電の普及によって再エネ賦課金が増えており、これ以上の負担増加を抑制するために、売電単価を下げているという理由もあります。
今後どうなる?
前の項目で触れたように、近年のFIT制度適用時の売電単価は減少傾向にあります。
その理由は、太陽光発電の普及が進んだことによる導入コストの低下や再エネ賦課金の上昇にあるため、今後も太陽光発電の普及が進めばさらに低下していくことが考えられるでしょう。
実際に電力中央研究所の研究では、FITの買取価格は「。2020年度以降は12円/kWhから段階的に低下し、2030年度8.5円/kWh」と想定されています。
しかし、売電単価が下がっているからといって太陽光発電を導入するメリットが無くなってきているとは限りません。
なぜなら、FIT初期よりも太陽光発電の導入コストが下がっているからです。
また、FIT制度を使った売電以外にも、FIP制度の利用や自家消費など太陽光発電を使って利益を得る方法はあります。
以下にFIP制度や自家消費について詳しく解説していきます。
FIP制度への移行
FIP制度(Feed-in Premium制度)とは、FIT制度で普及した太陽光をはじめとする再エネ電力を、電力市場に統合することを目指して設立された制度です。
FIT制度と同じように、発電施設導入に必要な費用をもとに策定された「基準価格」に、毎月市場によって変動する「プレミアム」を加えた額で、再エネ電力を売電できる制度になっています。そのため売電価格は毎月変動します。
「基準価格」に加えてプレミアが上乗せされた金額で売電できるので、電力市場の状況次第では、FIT制度よりも高い金額で売電できる可能性があります。
基準価格はFIT制度と同じように、20年間固定となります。
基準価格の推移を表で見てみます。
| 年度 | 基準価格 |
|---|---|
| 2024年度 入札制度により決定※4 | (第20回9.2円/第21回9.13円/ 第22回9.05円/第23回8.98円) |
| 2025年度 入札制度により決定 | (第24回8.90円/第25回8.83円/ 第26回8.75円/第27回8.68円) |
資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.htmlプレミアムは基準価格から、前年度の市場平均や非化石市場の収入、バランシングコストなどを加味して計算された参照価格を引いた額となります。
参照価格の具体的な計算式は以下の通りです。
参照価格 = 前年度年間平均市場価格 + (当年度月間平均市場価格 – 前年度月間平均市場価格) + 非化石価値市場収入 – バランシングコスト
すでにFIT制度を適用している太陽光発電設備でも、申請すればFIP制度に移行することが可能です。
ただし、FIP制度の認定を受けることができる太陽光発電は出力が50kw以上となっております。また出力が1mw(1000kw)を超える設備の場合は自動的にFIP制度が適用されます。
自家消費もおすすめ
太陽光発電の導入メリットは売電収入だけではありません。
近年、コロナの流行やウクライナ情勢によるエネルギー需要の上昇から、電気代が高騰し続けているため、自家消費でより多くの電気代を削減することができるようになっています。
電気代の1kwh当たりの単価は電力会社によっても変わってきますが、一つの基準として全国家庭電気製品公正取引協議会の出している、新電力料金目安単価を参照すると31円が目安の電気代単価<として定められております。
この価格は、2025年度の住宅用太陽光発電のFIT価格15円と比較しても倍以上の差があります。つまり、太陽光発電を導入すれば、自家消費によって充分な金額の電気代を削減できるだけでなく、余剰売電でさらに収入も得ることができます。
何年で投資が回収できる?
では、自家消費で節約した電気代とFITを使った売電収入を合わせて何年で元が取れるか試算してみましょう!
初期費用
今回は、発電出力が30kwの産業用太陽光発電を導入した場合を想定します。産業用太陽光発電の1kwあたりの必要経費は屋根設置(10kW〜50kW):15.0万円/kWと言われています。
出力が30kwの規模だと、450万円が必要経費となります。
年間売電収益
太陽光発電協会によると、出力が1kwの太陽光発電の年間発電量は約1000kwhです。 よって、30kwの産業用太陽光発電の年間発電量は30000kwh
経済産業省の資料によると、屋根設置型産業用太陽光発電の自家消費率の平均は近年だと約46%です。4.6割を自家消費したとすると、売電した電力は残りの5.4割
売電した電力は、30000×0.54=16200kwhであることがわかります。
30kw出力の太陽光発電の売電単価は1kwhあたり11.5円(上の表参照)なので、
年間の売電収入は11.5×16200=186300円
年間の売電収入は、18万6千300円と想定されます。
自家消費額
では次に自家消費によって節約した電気代を計算してみましょう。
30kwの産業用太陽光発電の年間発電量は30000kwh、また屋根設置型の太陽光発電の年間売電自家消費率は平均して約46%。
1年間で自家消費した電力量は、30000×0.46=13800kwhとなります。
新電力料金目安単価を参照して1kwh当たりの電力単価を31円とすると、
年間に削減した電気代は、13800×31=427800円(42万7千800円)となります。
先ほど試算した、年間の売電収益と合わせると、おおよその数値にはなりますが年間約60万円程度の費用を回収できていることがわかります。
初期費用450万を60で割ると、450÷60=7.5
よって、8年目で初期投資を回収できることがわかります。
卒FIT後はどうしたらいい?
FIT制度では、産業用は20年、住宅用は10年で買取期間が終了し、FIP制度でも20年間で買取期間を満了してしまします。
では、FIT/FIP終了後はどのように売電すればいいのでしょうか?
FITの買取期間を終了することを、一般的に卒FITと言います。
卒FIT後の売電方法について説明します。
結論から言うと、基本的に再契約や更新の手続きをせず、買取契約が自動更新される電力会社がほとんどです。ただし、FIT期間と比べて買取価格が大幅に下がってしまう可能性があります。
現在の大手電力が視野の電力買取プランでは、1kwh当たり8円程度が相場と言えます。そのためFIT期間と比べるとどうしても、売電収入が下がってしまいます。
対策としては、2つ考えられます。
1つ目は、より買取価格が高い電力会社と契約しなおすことです。
FIT期間終了後、現在契約している電力会社で充分な売電収入が期待できない場合は、契約を取り消して別の電力会社に余剰電力を売電するというのも手段としてかんがえられます。
2つ目は、余剰電力を売電せずに自家消費量を増やすという方法です。
昨今電気代が高騰していることもあって、どちらかといえばこちらの方がおすすめです。蓄電池を導入すれば、使いきれなかった電力を貯蔵することができるので、自家消費量を増やすことが可能です。
更新日:2025年11月26日






